2016.09.7
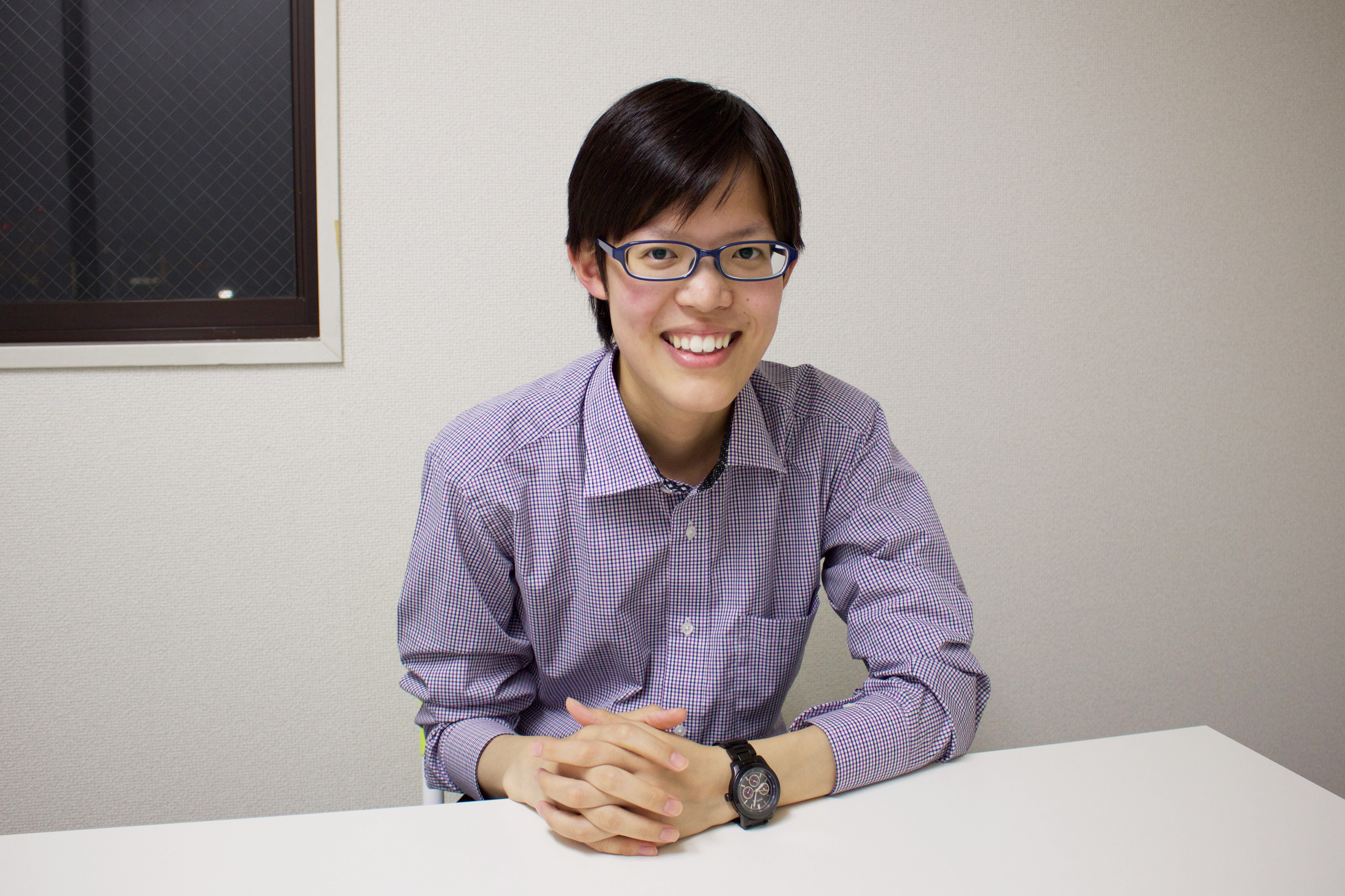
所属:都内ベンチャー企業
役職:営業職を経て販売企画部門課長
年齢:26歳
セクシュアリティ:FtX、女性ではないという自認
インタビュー日:2016年07月24日
ナカジマジュン
自分ってなんか周りとうまく馴染めていないな、っていうもやもやした感覚は小さい頃からありました。
強烈に覚えているのは小学校の入学式かな。
今はランドセルの種類も増えたけど、その頃って女の子は赤、男の子は黒って暗黙の了解で決まっていて。でも自分は赤いランドセルが嫌で、黄色のランドセルを買ってもらったんです。親も特に何も言わずそれを買ってくれました。幼少期から「女の子なんだから」とか全く言われなくて、幸運にも家庭内で男女分けへの違和感を抱く機会はなかったんです。
だから、入学式で黄色のランドセルの子が自分以外に全然いないことや、目立ってからかわれることにびっくりしました。
クラス分け表に書かれた自分の名前が赤い文字なのも不思議に思った記憶があります。「なんで赤なんだろう? 黒の方がよかったのにな」とは思ったけれど、それが男女分けの意味だとはわかっていませんでした。でもその赤い自分の名前は今でもよく覚えているし、嫌だった感覚も思い出せます。
それで、高校2年生の時に、自分のセクシュアリティを自覚する出来事がありました。
自分と仲の良い女の子の友達がいて、いつもどおり仲良くしていたらそれを見た別の友達から、「二人ほんとに仲良いね〜、カップルみたいだね」って言われて。悪意も何もないただの感想だったんでしょうけど、その言葉を聞いた時に、「今まで自分が感じてきたもやもや感って性に関することが原因だったのかもしれない」「自分は女の子が好きなのかもしれない」って初めて思ったんです。
そういえば男の子を好きになったこともないし、周りの女子が「(男子の)◯◯君カッコイイよね」と話しているのにもついていけなくて、それが自分の浮いている感じにも繋がっていたと気づいたんです。あと、制服でスカートを履くのもすごく嫌だったし。
それから家で、家族が寝た後にインターネットで色んな検索をしてみました。そうこうするうちに「トランスジェンダー」という言葉に出会ったんです。
初めて「世の中には割り当てられた性別と違う性別で生きている人がいるんだ」と知りました。
それでまたよくよく考えてみると、「別に自分は、男の子は好きになったことはないけど、女の子を好きになったこともないなあ」と気づいて、
「あ、じゃあこの違和感は〝誰を好きになるか〟ではなくて、〝自分が何者であるか〟っていう性の違和感なんだ」と思ったんです。
ネットで言葉を知ったことをきっかけに、自分はきっとトランスジェンダーなんだ、と初めて自分を名乗る言葉を手に入れました。とまどいよりも、一体自分は何者なのか?と悩んでいたところに名前が与えられた安心感がひたすら大きかったです。
ただその時同時に間違った認識も入ってきてしまって、自分は女性ではない! つまりこれから男性になっていかなきゃいけないんだ! と思い込んでしまったんです。
女性として生きていけないという感覚は自分の中で確かなものだったから、じゃあ男性になる、っていう極端な考え方しかその時は思いつかなかったんですよね。
ある種、やっとカテゴリーにはまれたっていう安心感を覚えたのかな。もうこの道しかないと思って、自分の体を嫌いにならなきゃいけないんだとか、自分の女性的な面を否定するようになりました。私服もよりメンズっぽいものを選んだり、男っぽいしぐさを研究して練習したり、典型的な「男性」にあてはまろうと努力をしていました。
ネットで得た情報だったから偏りもあって、その中の「セクシュアルマイノリティの人は東京にたくさんいるらしい」というのを鵜呑みにしちゃって、他の地域にはいないのかと思ったんです。それでどうしても東京に行きたくて、大学進学の理由を切り口に、母親にカミングアウトしました。
「今までずっと女の子として育ててきてくれたと思うんだけど、実は今まで一回も自分を女の子だと認識したことがないんだ。これからは男として生きていこうと思う。だから、東京へ行って自分と同じような人たちに会いたい。東京の大学へ行かせてください。」
一人娘と信じて疑わなかった我が子から突然のカミングアウトをされた母は、大号泣。
そして、ひとしきり泣いた後にこう言いました。
「男の子の体に産んであげられなくてごめんね。」
「気づいてあげられなくてごめんね。」
謝ってほしかったわけじゃないしママが悪いわけじゃないよと言ったけど、自分を責める母の姿は忘れられません。情報がないとカミングアウトする方もされる方も困るんだと実感しました。
僕が今LGBTに関する発信活動をしているのも、この時の母の印象深さが理由のひとつになっているのかもしれませんね。母はその後僕が置いていったLGBTに関する書籍を読んで勉強してくれたり、「LGBTの家族と友人をつなぐ会」に電話をして相談してくれて、最終的には僕を応援する形で東京の大学へ送り出してくれました。
うちは父母僕の3人家族で、父は大学入学時に母から僕の事情を聞いたそうです。その時の反応は「そうなんですね」とそのまま受け止めるような感じだったらしいです。世間体を全く気にしないタイプだったからかもしれませんね(笑)。
でも、父なりに応援してくれているんだと感じることがありました。
例えば、うちの家族は新年に海外向けのグリーティングカードを出すんですけど、それまで僕のことを「She(彼女)」と書いていたのを「Jun」と名前表記にしてくれたりとか。
それまでは受け入れられているか不安だったんですけど、嬉しかったです。
大学に入って初めて学校が楽しいと感じました。
研究室にLGBTの象徴であるレインボーフラッグが置いてあったり、教授が自己紹介で「自分はゲイ」と自然に話すこともあったんですよ。
セクシュアリティのみにとどまらず、多様性に富んだ大学だったから、徐々にカテゴリーに入っても入らなくても自分は自分、自然でいいんだと思えたんです。
性別への違和感を自覚してからは「男にならねば」と頑張ってきたけど、これってそれ以前の「女」という枠組みの中で振舞っていた時の息苦しさと変わらないじゃないかって気づいたんです。昔は女を演じていた、今は男を演じている、という状態だなって。
大学に入ってから性別じゃなく僕自身をみて仲良くしてくれる友達もいるし、「男」という存在にならなくても自分は人と関係性を結べる、そこに性別っていう要素は必要ないんだと思いました。
高校生の時に感じた「カテゴライズされる安心感」は大学生の僕にはもう必要じゃありませんでした。
その後Xジェンダーという言葉を知り「これこれ!」とも思いましたが、それよりも自分は自分、という認識の方が強かったですね。そう思わせてくれる仲間に出会えた大学4年間は本当に貴重だったと思います。
就職活動にさしかかると、色々と心配なことが出てきました。履歴書の性別欄やスーツ……就活のスタートラインで立ち止まってしまっている気がしました。
それに、トランスジェンダーやXジェンダーで一般企業で働いている大人を知らなかったので、そもそも民間企業で雇ってもらえるのか? とも不安に思いました。
でも大学の同期に相談をしたら、「もしセクシュアリティを理由に落とすような会社があるなら、そんなところで働かなくていいじゃん」と言ってもらえたんです。
ものは試しだと、履歴書の性別欄は空欄にして、スーツはメンズスーツ。どちらについても面接で事情を説明しました。
その前の説明会でも人事の方にセクシュアリティのことや気になることをガンガン聞いて、対応が好意的じゃない会社はこっちから弾いていましたね。
「前例がないので」と断られることもあれば、「我が社にもLGBTの社員はいます。履歴書には自分が思う性別を書いていただいていいですよ」と言ってくれた企業もありました。
だから面接に行った会社はその段階で対応が良かったところなので、面接で嫌な思いをすることはありませんでした。
最終的に就職した会社でも、「戸籍上は女性なんですが、女性としてではなく就労したいと思っています。」と希望を伝えていました。
内定の連絡でも、
「私たちの会社で中島さんのようなセクシュアリティの方が入るのは初めてなので、もしかしたらこちらの準備不足な点もあるかもしれません。だけどセクシュアリティに関係なく中島さんの人間性をみて一緒に働きたいと思ったので内定を出させていただきます。」
と言ってもらえて、ここで働こうと決めました。
まずは営業職に配属になりました。正直に実感したのは、「仕事ができればお客様も性別なんて気にされないんだな〜」ということでしたね。
直属の先輩が理解者だったのも大きいです。ある日僕と同行になった時にお客様が先輩に向かって僕を指して、
「この子はどっち? 女の子として扱えばいいの? それとも男の子?」と聞いてきたんです。
先輩は間髪入れずに、「いや、一営業として扱ってください。」と言ってくれました。
セクシュアリティ関係なく、ひとりの人間として扱ってくれる人が社内にいるだけで心強いですね。
その後配属は変わりましたが、セクシュアリティに関して嫌な思いをすることは未だにありません。
僕は子供の時、自分が大人になるなんて思っていなかったし、ましてや仕事をするなんて想像もつかなかったです。
でも今責任を持って働いていて、LGBTの大人という立場から発信活動をする場面もあって、本当に予想だにしなかった日々を過ごしています。
しんどい時って、もう明日も見えないような気持ちになると思うけど、このインタビューを読んでくださっている皆さんも、「自分も大人になれるんだ」って信じてみてほしいです。
僕は大人として、今悩んでいる人やこれから生まれてくる子どもが自分らしく生きられる社会にするために努力を続けようと思っています。
頑張る大人がいる限り社会は変わっていくと信じているので、もし今辛くてももうちょっとだけ明日を待ってみたら、僕みたいに思いがけないハッピーな日々が待っているかもしれません。
(取材・文・写真 角 亜維子)